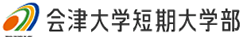本実習は、 食物栄養学科 2年生が前期に履修する科目です。臨床栄養学概論および臨床栄養学演習で学習した理論を土台として、傷病者の病態や栄養状態の特徴から、作成した献立を効率的・衛生的に調理が行えるようになることを目的としています。献立はテーマ毎に全員が作成し、実習では当番1名の献立を班全員で調理しています。献立作成当番は、全員が 2~3回担当になるように、順番を決めています。自分の班の食事を試食した後は、他の班の食事も試食し、お互いに評価し合います。エネルギーや栄養素の充足だけでなく、味や盛付方法・見た目にも気を配った献立作成から調理を心掛けています。
献立作成では栄養素を基準量まで充足するのに四苦八苦したり、調理では時間内に朝昼夕の 3食分を作り終えるために、協力し合ったりしています。普段食べている食事とは異なり、塩分やたんぱく質が制限された食事、濃厚流動食などの試食も行うため、実際に患者さんの立場になった体験ができることが特徴です。夏季休業中、病院などに学外実習に行くので、実習にも身が入ります。

↑一般治療食(朝食例)

↑塩分コントロール食 塩分1日6g未満(昼食例)

↑脂質コントロール食(朝食例)

↑脂質コントロール食(昼食例)

↑たんぱく質および塩分コントロール食(夕食例)

↑軟食・ソフト食献立例

↑治療用特殊食品を利用した献立例