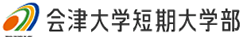幼児教育・福祉学科
(2023年度から幼児教育・福祉学科に変更)

幼児教育・福祉学科で学ぶこと
幼児教育・福祉学科では、地域の未来を担う子どもの育成に誇りを持ち、子どもに愛情と情熱を注ぎ、かつ、高い倫理観と自律心を持った教師、保育士、保育教諭、また、子どもの背景になる様々な社会、環境問題について理解し、具体的解決にあたることができるソーシャルワーカー(社会福祉士)を育てることが、その使命であると考えています。よって卒業必修科目として「教育学概論」「保育原理」「保育の心理学」などの教育・保育の基本を学ぶとともに、「保育内容総論」など具体的な子どもへの指導法について学びます。また、「幼児と健康」「幼児と人間関係」「幼児と環境」「幼児と表現Ⅰa」といった保育の専門知識と方法を学びます。これらの教職関連科目は児童養護施設や障がい児施設などの児童福祉施設といった福祉の専門領域でも必要とされている学びです。さらに自由科目として社会福祉士受験資格関連科目を履修することも可能で(一定の条件を満たすことが必要です)、教師、保育士、ソーシャルワーカーの連携(専門職連携)についても学びます。
■幼児教育・福祉学科のアドミッション・ポリシー(入学者受入方針)
- 子どもをはじめ、すべての人々を取り巻く環境の変化や諸問題を理解する基礎学力があり、自ら学び考える人
- 子どもをはじめ、すべての人々の個々の尊厳と権利を深く理解し、現代社会の抱える諸問題に向き合っていける人
- 幼児教育・社会福祉における専門性と倫理観を身につけて、地域社会において貢献しようとする意欲がある人
■幼児教育・福祉学科のカリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施方針)
幼児教育・福祉学科の教育課程は、教育研究上の目的を達成し、学位授与方針に掲げた能力の育成のため、教養基礎科目、専門教育科目、自由科目をもって編成する。
「教養基礎科目」では全人的な豊かな人間性を醸成するため幅広く教養分野を学ぶ。
「専門教育科目」では幼稚園教諭免許取得に関する科目、保育士資格取得に関する科目を中心に必修科目、選択必修科目を設置する。
「自由科目」では、社会福祉系科目を充実させ、社会福祉士国家試験受験資格取得が可能であり(要2年の相談援助実務経験)、地域からの人材需要にも対応するとともに、特に幼児教育・保育と関連する福祉分野についてさらに深く学びたいという学生の希望に対応できるように科目を配置する。加えて、高齢、障がい、貧困等の社会的ニーズについて幅広く対応できる人材育成のための科目を配置する。
さらに本学科の特性を生かし、教育・保育・福祉の連携によるIPE(多職種連携教育)演習を2年生全員参加で実施し、専門職者としての協働性を醸成する。
本学科では、教育・保育・福祉の各専門性とその連携について学ぶことができる環境である特徴を生かし実践力のあるジェネラリスト養成を可能とする科目構成としている。
<専門教育科目について>
-
幼児教育系
1年次において教育分野における基礎的専門知識・専門技術・指導法を修得するとともに権利尊重を基盤とした倫理観を醸成する。
2年次において、さらに専門性を深化、応用した専門知識・技術を修得後、幼稚園・こども園において教育実習を実施し、幼児教育現場から提起される問題・課題に触れる体験を通してこれまでの学修内容の振り返り、整理、課題の抽出を行い次の学修へと結びつける。
後期においては実習の事後指導に加え、これまでの学修成果を振り返り(履修カルテを活用)、就労前教育の仕上げとして「教職・保育実践演習」を実施する。 -
保育系
1年次において保育分野における基礎的専門知識・専門技術・指導法を修得するとともに権利尊重を基盤とした倫理観を醸成する。
1年次の学修後に保育実習Ⅰa(施設実習)を実施する。現場において、短大で学修したことと実際の臨床から提起される問題・課題に触れる体験を通じ、これまでの学修内容の振り返り、整理、課題の抽出を行い次の学修へと結びつける。
2年次において、さらに専門性を深化、応用した専門知識・専門技術を修得後、保育実習Ⅰb(保育所実習)を実施し、幼児教育・保育現場から提起される問題・課題に触れる体験を通じ、これまでの学修内容の振り返り、整理、課題の抽出を行い次の学修へと結びつける。
その後保育実習Ⅱ(保育所実習)、保育実習Ⅲ(施設実習)いずれかを選択し自らの進路を見据えた上での実習を行う。
それぞれの実習の事後指導に加え2年次後期では実習を終了した時点でこれまでの学修成果を振り返り(履修カルテを活用)、就労前教育の仕上げとして「教職・保育実践演習」を実施する。
<自由科目について>
-
社会福祉系
1年次、2年次前期においてソーシャルワーク(個人やグループ、コミュニティが直面する課題を解決し、生活の質を向上させるための専門的な支援活動のこと)における各分野の基礎的専門知識・専門技術を、さらに専門性を深化、応用した専門知識・技術を修得し、2年次のソーシャルワーク実習に臨む。これまで学修したことと実際の臨床から提起される問題・課題に触れる体験を通じ、これまでの学修内容を振り返り、整理、課題の抽出を行い、さらなる学修へと結びつける科目で構成する。その成果は実習報告書にまとめると同時に実習報告会で発表する。さらに、現在も継続されている復興支援について学ぶ「復興支援の実際」を配置する。 -
幼児教育系
即戦的実践力獲得を目的に「こども実践演習」「発達障害幼児療育法」で構成している。
■幼児教育・福祉学科のディプロマ・ポリシー(学位授与方針)
会津大学短期大学部では所定の期間在学し、かつ本学の教育目標ならびに各学科で定める教育研究上の目的に基づいて設定された授業科目を履修し、所定単位数を修め、以下の知識、能力を修め、卒業認定された学生に対し学位(短期大学士(産業情報)、短期大学士(食物栄養)、短期大学士(幼児教育))を授与する。
<幼児教育・福祉学科>
幼児教育・福祉学科では、教育、保育、福祉に関わる基礎から応用、そしてそれらを統合し活用することができる協働力、実践力にわたる学術分野を教授することにより、人間尊重の理念に基づき豊かな人間性と実践力を通して社会の発展に貢献できる人材の育成を図る。
これを達成するために本学科では、以下の能力を身に付けた学生に対して学位を授与する。
- 本学科で学んだ知見、技能と現場での体験を統合的に理解し、謙虚に自身の専門職としての資質を振り返ることができる姿勢
- 子どもをはじめ、すべての人々に対する尊敬と愛情を持ち、一人ひとりへの関心を持つとともに、多様なニーズに対応できる専門知識と技術
- 子どもをはじめ、すべての人々の権利尊重を基盤とした倫理観と、インクルーシブ、ダイバーシティ的視点を持ち、社会に存在する諸問題解決のために社会資源を活用することができる実践力と科学的洞察力
- 均衡のとれた全人的教養と人間性
- 教育、保育、福祉の専門知識、専門技術、専門職倫理を統合し問題解決にあたる協働力
(産業情報学科・食物栄養学科については省略)